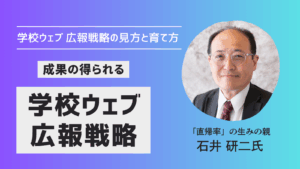山𦚰 克孝 氏/アートディレクター・クリエイティブプランナー
今回は、神戸市在住の山𦚰 克孝氏にお話を伺いました。アートディレクター/クリエイティブプランナーとして、広告・ブランディングをはじめ、プロジェクトの上流設計からクリエイティブの実装まで幅広く手がけています。
山𦚰さんの特徴は、その学校や組織が持つ本来の魅力をどう引き出し、どう伝えるかまでを考え抜くこと。表には見えにくい部分にまで丁寧に向き合い、デザインを通して魅力をカタチにしていきます。教育・学校分野の実績も豊富で、高校や大学、専門学校の広報・ブランディングで成果を上げ、教育機関の魅力を引き出すパートナーとして厚い信頼を得ています。
多視点から始まる企画づくり
私は普段、アートディレクター/クリエイティブプランナーとして活動しています。ですがその前に、一人の生活者として相手の話をよく聞くことを大切にしています。クリエイターとしてこう見せたい、こんな表現にしたいということではなく、先入観を持たずに受け止めること。そのうえで、多視点から問いを立て、「もし自分がその立場だったら」と想像力を膨らませて考えていきます。
たとえば、生徒はどんな感情を抱えているのか、保護者は何を不安に思い、どこに期待を寄せているのか、先生方はどんな課題を感じているのか。そうした要素を一つひとつ丁寧に組み立て、仮説を立てながらアイデアをカタチにしていきます。そこから課題の所在や改善すべき点を見極め、会話を重ねることで企画の軸を見つけていく。私にとっての出発点は、いつもそこにあります。
『視点・仕組み・仕掛け』でつくる広報戦略
私は『視点・仕組み・仕掛け』の3つの要素を大切にしています。この3つがバラバラに機能していては、本質的な改善にはつながりません。まず大切なのは、どのような『視点』で広報を考えるかです。つまり、学校が本当に大切にしていることは何かという視点です。教育理念や教育目標とズレてはいけないのはもちろんですが、目の前の現実を見つめることも欠かせません。たとえば、中学2年生の受験生の多くは、まだ自分の将来を明確に描けていません。保護者にとっても、子どもの未来は未知数です。だからこそ、学校がその可能性を磨き、育んでいくという視点を持つことが重要です。逆に昔からの慣習だから、長年付き合いのある業者だからという理由だけで広報物をつくってはいないでしょうか。時代は令和。受け手の価値観も、学校が示すべき教育の姿も、日々変化しています。
次に必要なのは、それを確実に届けるための『仕組み』です。どれだけ質の高いクリエイティブでも、それを支える仕組みが弱ければ成果にはつながりません。SNS、Web、紙媒体、地域との接点などをどう組み立てるか。この仕組みこそが戦略全体を左右します。私が実際に関わった事例では、同じ予算内で配布物の組み立てを見直しました。従来はボリュームのある学校案内でしたが、保護者には要点を絞った16ページのパンフレットを、受験生にはタブロイド版を制作して年2回配布。対象に合わせてメッセージを最適化することで、内容が伝わりやすくなると同時に、接点の回数も増やすことができました。限られたリソースをどこに配分するかを見極めることが、広報全体の仕組みをカタチづくります。
そして最後に、どう伝えるかという『仕掛け』の部分。Webサイト運営、動画配信、SNS投稿などの目に見えるクリエイティブは、アウトプットとして最も注目されがちですが、本当に伝わる広報とは、仕掛けが先行するものではありません。どんな視点で捉え、どんな仕組みで届けるかがあってこそ、これらクリエイティブの力が最大限に発揮されます。この3つが連動して初めて、学校らしさが届く広報になります。
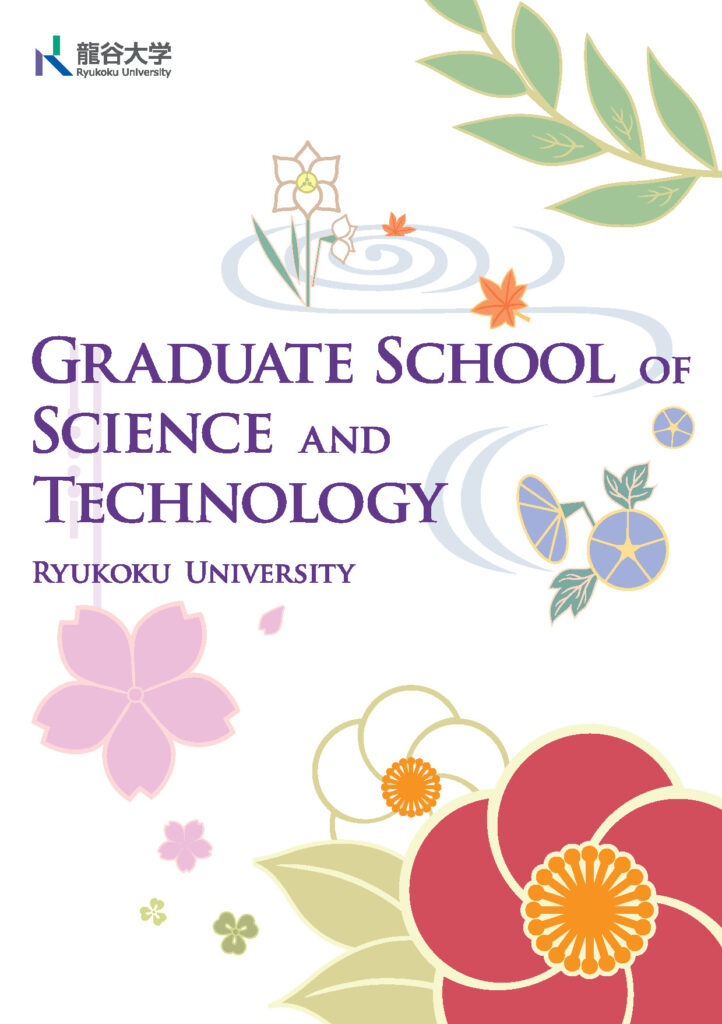
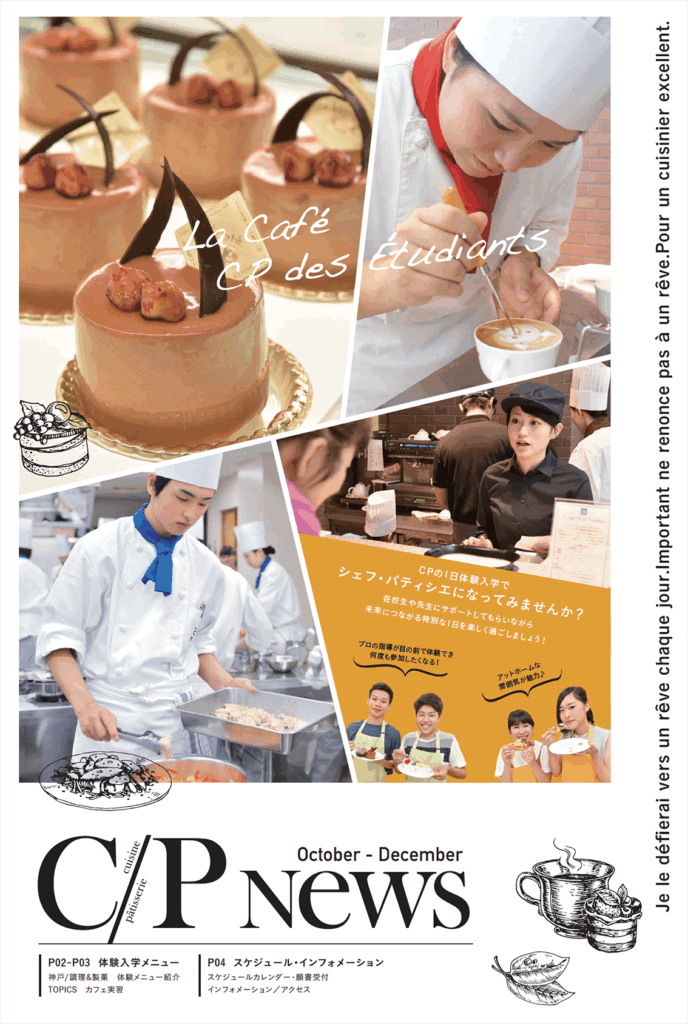

学校全体の力を広報へ
数年前、私は定員割れが続いていた学校のブランディングに関わりました。振り返って感じるのは、先生方が「この状況を変えよう」と本気で覚悟を決めておられたことです。理事長をはじめ、現場の先生方が一致団結し、学校全体として前進しようという強い意志がありました。その熱意があったからこそ、私たちが提案した『視点・仕組み・仕掛け』のフレームを現場に落とし込み、具体的なクリエイティブとしてカタチにすることができました。結果として、広報活動は新しい学校のイメージを切り拓く力となり、受験生や保護者に強く訴求するものになりました。そして最終的に、定員を満たす成果へとつながっていきました。

答えのない時代に、問い続けるデザイン
私にとってデザインは目的ではなく、課題を解決するための手段です。クリエイティブに関わる以前に、課題を解決したいという想いや情熱、好奇心があります。 だからこそ、私は現場に足を運ぶことを大切にしています。オープンキャンパスや文化祭、地域行事などに出向き、生徒たちの空気に触れ、先生方と一緒に悩み、ときに迷いながら考える。その姿勢があってこそ、先生方との信頼関係が育まれます。
もし企画に熱が感じられないとしたら、それは制作側と現場との間に距離ができているのかもしれません。変化の激しい社会において、誰も答えを持っていません。だからこそ必要なのは、考え、問い続ける姿勢を持つこと。そして、対話や発想のプロセスにあるような、数値では測れない余白の価値を見出すことだと思います。答えのない時代に、こうした姿勢を次の世代へと手渡すことも、教育の大切な役割なのかもしれません。