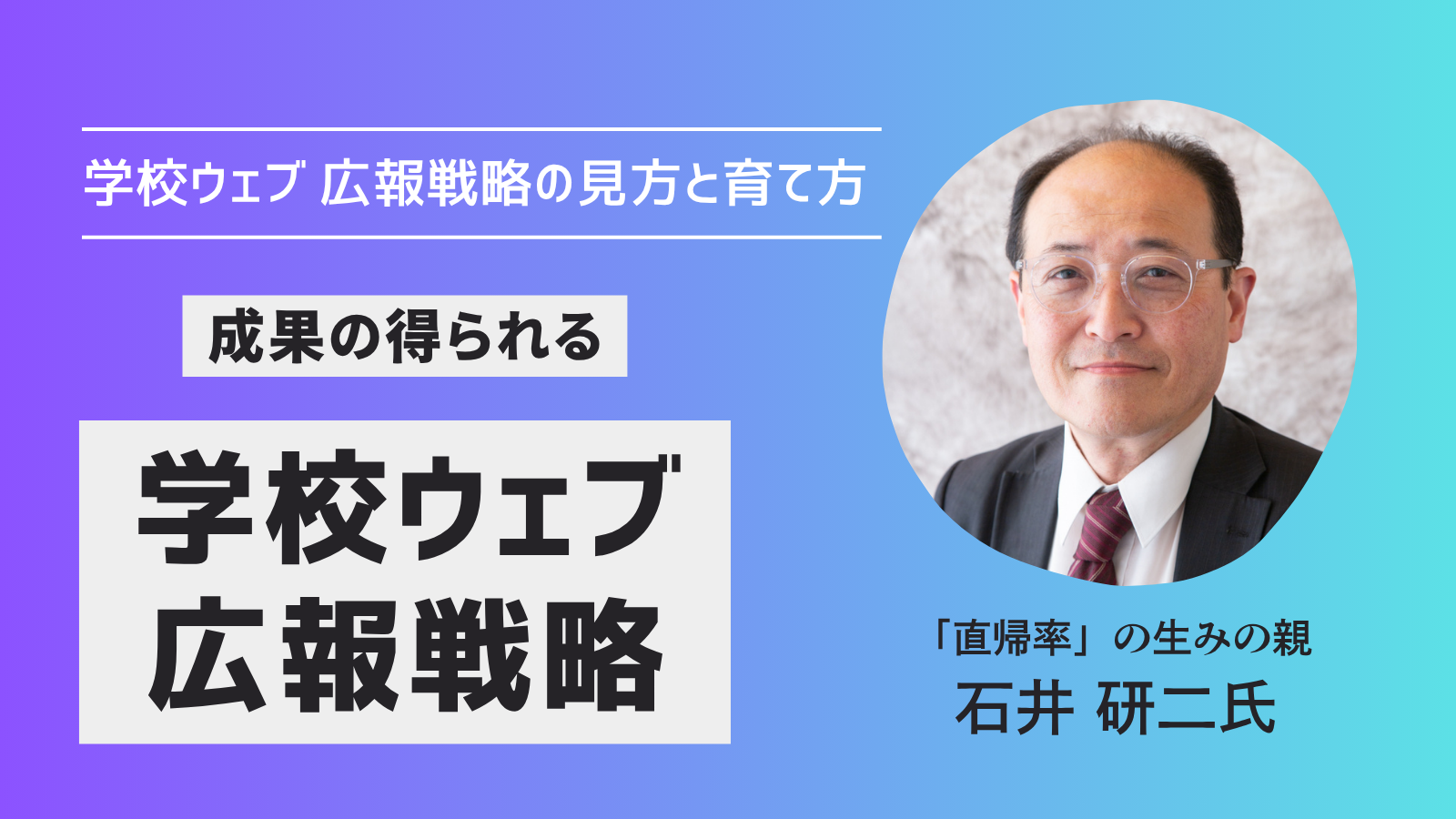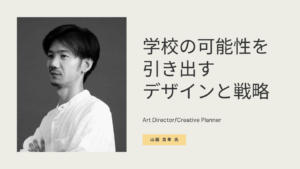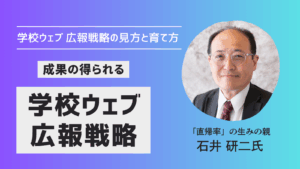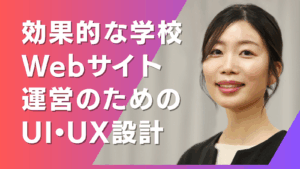【第3回】学校ブランディングのためのウェブサイト作成法 就職実績と留学情報以外の「差」
ブランディングとは「唯一の言葉」を占めること
少子化の中で学校が競争を生き抜いていくためには、「選ばれる学校」になることが不可欠です。
学校ブランディングを考える際には枕詞に地域名を冠するようにしましょう。つまり、「〇〇地域で一番□□な学校」という考え方です。
この□□が、学校を地域一番の存在にするために欠かせない言葉となります。自動車を考えてみましょう。「安全」という言葉で思い出すのはどの車でしょうか。ボルボあたりが思い浮かぶのではないでしょうか。ボルボはこの意味でブランディングに成功しています。ブランディングとはこのように唯一の言葉を占有する作業なのです。
「進学率・就職率」や「留学のしやすさ」などを打ち出す学校も多いですが、それを打ち出せば打ち出すほど、他の学校のアピールに似てしまう場合があります。もちろんそこで他校に負けてはいけないかもしれませんが、そのポイントとは別の「独自性」を見つけなければなりません。
自校の特徴、歴史を顧みて、どんな言葉が思い浮かぶか。今後、どのようなイメージを獲得していきたいのか。競合校とポジショニング比較をして、どこが推しポイントなのか。それらを打ち出すようにしていきましょう。
ただ、ホームページにする際にはパンフレットなどとは違う注意点があります。
学校ブランディングのためのホームページをつくる3つのポイント
①ホームページを訪れたすべての人が気づくか?
ホームページとパンフレットの大きな違いは「表紙を見ない人が非常に多い」点です。ホームページではトップ以外のページから見始める人が非常に多いのです。トップは20%の人が見るかどうか。月に1,000人が見に来る場合、200人がトップページを見ていれば多い方です。
オープンキャンパスの告知ページに広告を出して、そこに直接誘導している場合には、1割もトップページを見ない状態となります。
外部のポータルサイトから「入試情報」にリンクしている場合も、トップの閲覧率を引き下げます。
Google検索では「〇〇校 学費」「〇〇校 難易度」といった検索を行う人が多くなります。その際に、どのページが紹介されるかには注目しましょう。そこが、閲覧のスタートになる可能性が高いからです。
学費のページや入試情報のトップなどが、事務的な内容伝達ページになっていませんか? そのページから見始めた人が、ブランディングメッセージに気づくかどうか。
トップページは期待するより見られていません。そこにだけブランドメッセージを掲載して、あとのページでは目につかないのではイメージを浸透させられません。全ページでメッセージを印象付けられるかどうか。トップのデザインよりも、全ページのテンプレートのつくり方が重要と考えてください。

②ブランディングでは、全体での徹底が肝心
ホームページは入試広報だけの考え方でつくるものではありません。学校全体の広報と入試広報のイメージづくりがずれていることが少なくないようです。そのためメッセージが徹底されず、「学校案内」部分と「入学者募集」部分でイメージが分かれてしまっているホームページが多いのが実際です。
中高一貫校では中学と高校で見え方が違う場合もあります。意図して「見せ方」を分けるのは良いのですが、単につくりが違ってイメージがぶれていては損をします。大学では学部ごとに意見が異なって、重要なメッセージが薄れてしまう場合が少なくありません。
ホームページを見に来た人は、どんな順番でどのページを巡回しているでしょうか。「カスタマージャーニー」を再現してください。お客様が見る順序で、実際にサイトを見ていき、ブランディングメッセージが安定して伝わるように、徹底していきましょう。
③ブランディングではイメージの反復が欠かせない
ブランディングでは、イメージを頭に定着させることが不可欠です。自動車の例で言えば、「メルセデスベンツ」という名前を思い浮かべられる人は多いですが、正確にそのスペルを書ける人は少ないかもしれません。何度も反復されるうちに、音韻として頭に刻まれているのです。目からの情報は重要ですが、最後は音韻として残るかどうかです。
受験校選びでも「3校受けよう」と考える中で、その3つの中に入れるかは、頭に音韻として残っているかが大きく作用します。そのためには「反復」を考える必要があります。
ホームページには反復の仕掛けがいくつもあります。第1に、複数回サイトを訪れさせること。その時に学校名やメッセージが目に入り頭に残ります。実は、入試情報やオープンキャンパスのページだけ、学校名を英語表記するなどして、印象を変えてしまっているホームページが多いいので注意が必要です。
第2に、ホームページはスクロールして見る媒体です。上部で見せたメッセージが、ページの下部で反復されてやっと頭に定着します。スマホを意識して、ホームページの上部にもメッセージがなく、一番下のフッタ側にも何もメッセージがないホームページが増えていますが、反復を意識してしっかり点検しましょう。
第3に、ホームページはページからページへ遷移して情報を得る媒体です。その際、順不同で見られるのが普通です。複数ページを巡回する中で、どんな順番で見た人にも、繰り返し学校名やメッセージが伝わっていくようにしなければなりません。
重要な指標に「平均ページ数」があります。1回の訪問で、平均何ページを巡回したか。それが多いほど、ブランドの定着効果が高いと言えます。一般に、初訪問時は得たい情報が多いので平均ページ数が多く、夏以降には目的がはっきりしていて平均ページ数が下がる傾向があります。その場合にも、「あと1ページ見てもらう」にはどうすれば良いか、効果的な仕掛けを盛り込んでください。
ホームページは年度の初めにつくったら終わり、になっていませんか? オープンキャンパスの日程やニュースの更新だけではなく、ターゲットの反応を見て情報を追加していくことも欠かせません。そこで次回は、「ウェブの反応を見て改善・情報追加をするために」について考えていくことにしましょう。